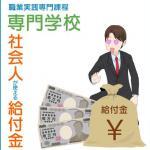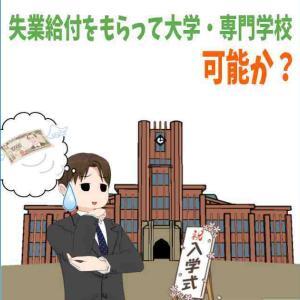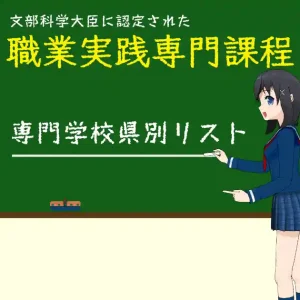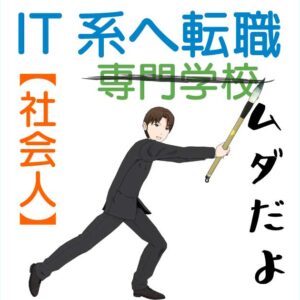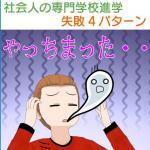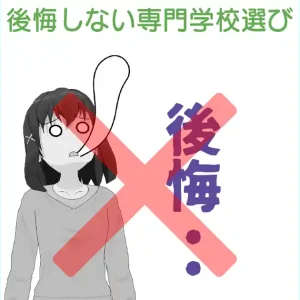職業実践課程に認定された専門学校の学科であれば、国が認めたレベルの教育水準を期待できます。
本記事では職業実践専門課程について解説し、そのメリットとデメリットを考えてみたいと思います。
職業実践専門課程とは

職業実践専門課程について、法的には下記のように規定されています。
第一条 〜前文省略〜 職業に必要な実践的かつ専門的な能力を育成することを目的として専攻分野における実務に関する知識、技術及び技能について組織的な教育を行うもの(以下「職業実践専門課程」という。)を文部科学大臣が認定して奨励することにより、専修学校専門課程における職業教育の水準の維持向上を図ることを目的とする。
ようするに、専門学校の質の向上を狙ったもので、実務に関する知識や技術に重点をおいています。
即戦力の人材を養成するのが専門学校でしょ、職業実践課程はさらに期待できるってことね!


その通りです。どうせ選ぶなら職業実践専門課程が良いでしょう。
この職業実践専門課程はどんな専門学校でも認定されるというわけではなく、法律で定められた認定基準をクリアしている専門学校が申請・審査されることで認定されます。
全国の専門学校のうち、職業実践専門課程に認定された学科を有するのは全体の約40%程度しかありません。
約4割・・思ったより少ないのね・・

職業実践専門課程のメリット

職業実践専門課程のメリットは大きく3つあります。
職業実践専門課程のメリット 1 企業と連携したカリキュラムと教育体制
この制度の大きな目的は、職業に直結するスキルを高度に学べるように専門学校の教育の質を確保することにあります。
なので、職業実践専門課程のカリキュラム編成は、企業や業界の人がメンバーとして参加する「教育課程編成委員会」が行うルールとなっています。
業界人がカリキュラム全体を見渡し検討するため、実践的かつ体系的なカリキュラムが編成されます。

企業が欲しい人材像が具体的にカリキュラムに反映されると言えます。
企業が欲しいってことは就職しやすくなるだけでなく、即戦力になれそうね!

職業実践専門課程では企業と連携した授業が展開されます。
具体的に企業側は「社員を講師として派遣」「実習場所・実習内容の提供」「インターンの受け入れ」という対応が挙げられます。
一方、学生は実際の仕事現場に触れることで、例えば学習到達目標を具体的に肌で感じ取れたり、最新の技術に触れたりすることができます。
仕事や企業のイメージがバッチリ掴めるわね!

職業実践専門課程のメリット 2 情報公開による安心感
多くの専門学校の広告では就職率100%とか高い合格率といった文言が踊っていますが、本当にそれが正確な(正直な?)数値かどうか判断する必要があります。
例えば、パンフレット等で就職率は「就職を希望する人のうち就職できた人」の割合を就職率として公表するのが通例です。
卒業者に占める就職者数じゃないのね・・?
ってことは・・
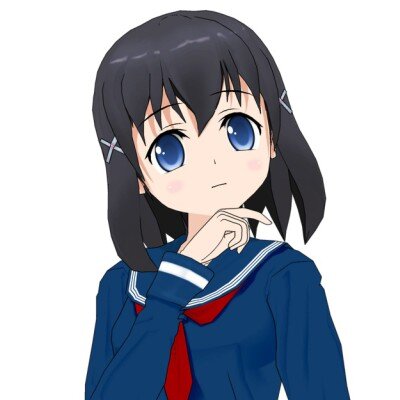

就職を希望せずに卒業する人が大量にいるケースも考えられるのです(進学を除く)。
なんかヤバそうね。


ネットやSNSでも度々話題になる、専門学校の闇の部分ですね・・
職業実践専門課程に指定されている学科の情報は、決められた様式での情報公開が法令で定められており、誰でも現実的な情報を見ることができます。
そしてこれは嘘・偽りの情報を公表することはできません。
過去に、この書類に虚偽記載して認定を取り消された専門学校もあります。
嘘ついてた学校あるんだ・・最低ね。


行政に出す書類も虚偽記載するぐらいですから、公式サイトやパンフレットの記載は注意深く見る必要がありますね。
なお、高等教育の修学支援制度(大学等無償化)制度の認定校も似たような情報公開が義務付けされていますが、若干公開内容が異なります(下表)。
| 職業実践専門課程 | 教育内容の質について把握できる公開内容。例えば企業と組んでどのような教育を目指しているか?実際の状況は?とか。専任教員の学歴と割合。他に、詳しい就職状況(地元就職率や卒業者に占める就職者数)。留学生の数など。 |
|---|---|
| 高等教育無償化 | どちらかというと、学校としての体裁を示す情報を公開。例えば成績の付け方、卒業要件。学校法人の財務状況など。 |

両方の公開情報とパンフレットを参照すればより深く理解を深められます。
職業実践専門課程のメリット 3 給付金で経済的負担の軽減(社会人)
一定の条件を満たす社会人が専門学校で学び直す場合、国から結構な額の給付金を受けることができます。
詳しくは「社会人が専門学校の職業実践専門課程で学ぶときに使える給付金」という記事で解説していますのでそちらの記事をご参照ください。
職業実践専門課程のデメリット
入学希望の学科が職業実践専門課程であるデメリットは無いと思いますが、注意点があります。
職業実践専門課程に認定されるということは、カリキュラムが実践的で文科省所定の規定を満たしているというだけという点です。
つまり、認定に関して卒業生の就職先や試験の合格率などの実績は考慮されていないということです。
結局、パンフレットとかで比較検討しないとダメね・・


その通りです。
職業実践専門課程に認定されているからといって鵜呑みにせず、他校との比較検討は絶対に必要です。
職業実践専門課程に認定された専門学校の探し方
本サイトでは各都道府県ごとの職業実践専門課程及び高等教育修学支援認定についての一覧を提供しています。
ご覧になりたい方は「職業実践専門課程」の県別「認定専門学校・学科リスト」をご参照ください。